【健康経営の情報】メンタルについて今回は、最新号のプレジデント誌 2025年8/15号の特集から、「気分の整え方」①感謝〜⑥食事についてまとめてみました。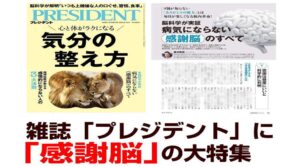
① 感謝編:脳科学で証明された「ありがとうの力」
精神科医・樺沢紫苑さんによると、感謝の表現は「病気になりにくい脳」をつくる鍵です。日常的に「ありがとう」を伝えることが、脳内ホルモンの好循環を促し、幸福感や運気アップにつながると解説されています。これこそ「感謝脳」の力です。
② 感情編:「いい人」を卒業して不機嫌を卒業
精神科医・和田秀樹先生による「いい人」をやめるための3大法則が紹介されています。誰にでも合うとは限らない期待に応えようとする行動が、不機嫌や疲れの原因に。自分の気持ちに正直になることが、気分の安定につながります。
③ 習慣編:スポーツドクターが提唱する「ご機嫌習慣」
スポーツドクター・辻秀一さんは、日常に取り入れられる“たったひとつの習慣”が、人間関係のトラブルや健康不安、不運を変える力になると説きます。継続しやすく、即効性のある方法がポイントです。
④ 話し方編:「言葉」が気分を左右する!
脳科学者・西剛志さんによれば、いつも上機嫌に見える人の話し方には共通パターンがあります。言葉遣いや声のトーン、フレーズの選び方で、自分も周りも元気にすることができると説かれています。
⑤ 自律神経編:「〜すべき」がストレスのもと?
順天堂大学の小林弘幸教授は、過度な「〜すべき」思考はストレスとイライラの温床になると警告。自律神経を整える具体的な方法を提示し、気分の乱れを防ぐヒントを提供しています。
⑥ 食事編:GABA・トリプトファン・ポリフェノールの威力
栄養を通じて気分を整える食事術。たとえばGABA(γ‑アミノ酪酸)、トリプトファン、ポリフェノールなどが含まれる食品を選ぶことで、「いい人」でいることが自然に支えられるという内容です。「スイーツは逆効果」という指摘も印象的です。
このように「気分の整え方」は、脳科学・医学・栄養学に基づいた具体的なアプローチが満載です。アザエンジニアリングでは、社員の健康と快適な職場づくりを大切にしています。